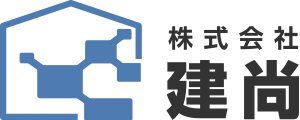こんにちは☀
ガイソー横浜港南店・町田店です!
外装リフォームについて情報収集をされている方は、「コーキング」という言葉を耳にしたことがあるのではないでしょうか。
一体何のためにコーキングを行うのか、具体的にどのような工程で行われるのかが分からない……という方もいらっしゃるかもしれません。さらに「シーリング」という似た言葉もあるため、非常にややこしくなっています。
しかし、コーキングは実は建物全体の耐久性を大きく左右する要素なので、しっかりと理解を深める必要があります。
そこで今回のコラムでは、 コーキング の役割とシーリングとの違い、具体的な工事工程について解説していきたいと思います!
コーキングとは?
コーキングとは、「目地(部材同士のつなぎ目)や隙間部分にコーキング材を充填する作業」のことです。また、充填されたコーキング材のことを指している場合もあります。
コーキング材はペースト状のシリコンであることが多く、目地材、シーリング材、充填材などの様々な呼び方があります。
コーキングを行う目的として、以下の3点が挙げられます。
- 目地、隙間部分からの雨水の侵入を防ぐ
- 建物の揺れ・収縮による外壁材の衝突・破損を防ぐ
- 下地のクラックを補修する
建物の目地や隙間部分にコーキングを行うことで、それらの箇所からの雨水の侵入を未然に防ぐことができます。
サイディングボードのつなぎ目や、窓・サッシまわりの隙間部分は雨水が非常に入り込みやすいため、ここにコーキングを行うことで建物全体の防水性を高めることができます。
コーキング材には、「外壁材の衝突・破損を防ぐ」という役割もあります。
地震の揺れや熱膨張・収縮などにより、建物は毎日のようにほんの少しだけ動いています。この建物の動きに外壁材が追随することで、外壁材同士がぶつかって破損してしまう可能性があります。
コーキング材をサイディングボードのつなぎ目に充填することで、外壁材が動いたとしてもコーキング材がクッションとなって衝突や破損を防ぐことができるのです。
また、コーキングは下地のクラックを補修するために行われることも多いです。
クラックとは、外壁や基礎部分などにできる亀裂やひび割れのことを指した建築用語です。地震によってクラックが発生することもありますが、基本的には下地の膨張・収縮や塗膜の乾燥などが原因として挙げられます。
ヘアークラック(幅0.3㎜以下、深さ4㎜以下の微細なひび割れ)であれば、通常の塗装工事(下塗り・中塗り・上塗りの3回塗装)を行うだけで綺麗に隠れますが、それ以上のクラックは隠し切れずに汚い仕上がりになってしまいます。
そこで、下塗りの前にクラック部分のコーキングを行うことで、3回の塗装でクラックをしっかりと隠せるようになるのです。
「クラックを補修した場合、その部分だけ浮いて見えてしまうのではないか?」と思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、コーキング材は基本的に白色のものを使用するため、下塗り塗料に馴染んで目立ちにくくなりますのでご安心ください。
コーキングとシーリングの違い
コーキングに似た言葉として「シーリング」というものがあります。
わざわざ別の言葉として存在するのだから、コーキングとシーリングは違う作業のことを指しているのだろうと思ってしまいますが、実はどちらも「ペースト状の目地材を目地や建物の隙間に充填する作業」とまったく同じ作業のことを意味しています。
では何故2つの言葉が存在しているのかというと、建築業界以外で用いられていた言葉が一緒に建築用語として用いられるようになったからです。
まず、コーキングは英語の「caulk」が語源となっており、これは「船の隙間に槙肌(まきはだ、まいはだ)を詰め込むことで船の水漏れを防ぐ」という意味の航海用語です。槙肌とはヒノキやコウヤマキの樹皮を砕いて繊維状にしたもので、船の接合部に使用されていました。
シーリングの語源となった「seal」は「液体や気体などの外部への漏出や、雨水や汚れなどの侵入を防ぐために使用される部品や素材」を意味した工業用語です。蒸気機関が発明された18世紀頃からシールの性能が重要視されるようになり、そこからシーリングという言葉が誕生しました。
これらの2つの言葉が一緒に建築業界に入ってきたことで、同じ内容であるはずなのに業者によって作業名が違うといったややこしい現状となってしまいました。
とはいえ、コーキングとシーリングの両方の語を用いている業者はほとんどいないので、「コーキング=シーリング」だということさえご理解いただければ問題ありません。
コーキングの劣化症状
コーキングも外壁や屋根と同じように、紫外線や雨風などによって劣化してしまいます。
コーキングの劣化が進むと防水性能が低下し、雨水の侵入を防ぐことができなくなってしまいます。目地や隙間部分からの雨漏りの原因となってしまうので、下記のコーキングの劣化症状が見られたら、早めのリフォーム工事を検討するようにしましょう。
コーキングの劣化症状として、以下の4点が挙げられます。
- 肉やせ
- ひび割れ
- 破断
- ブリード現象
肉やせはコーキングの初期の劣化症状で、「コーキングの可塑剤(材料に柔軟性・弾性を付与する添加物)が表面に溶け出し、厚みが減ってしまった状態」を指しています。
紫外線による経年劣化や、コーキング材の充填量が少なかった(施工不良)ことで発生します。
肉やせの段階では雨漏りが発生することはありませんが、肉やせからひび割れ、破断にまで進行してしまう可能性があるため、コーキングの劣化が始まっているとしっかり認識するようにしましょう。
コーキングの劣化が進行すると、コーキングの「ひび割れ」が発生します。
可塑剤のほとんどが失われてしまうとコーキングの弾力性も消失してしまい、外壁材の振動・収縮に対応できずにひび割れてしまうのです。
ひび割れが発生している時点でコーキングの防水性能は大分衰えており、ひび割れ部分から少しずつ内部に雨水が入り込んでしまうため、コーキングのひび割れを見つけたらメンテナンスの検討をおすすめいたします。

破断はコーキングのひび割れがさらに進行し、「コーキングの真ん中から裂けて穴が開いている状態」になります。
外壁内部が見えてしまっている状態なので、雨水に直接触れることで腐食が発生する可能性が非常に高いです。
かなり深刻な症状であるため、一刻も早くリフォーム工事を行う必要があります。
そして、ブリード現象は「表面に溶け出した可塑剤が外壁塗料と混ざり合うことで、コーキングが黒く変色すること」です。
コーキングの変色によって見映えが悪くなるというだけでなく、可塑剤が外壁の塗膜の耐久性に悪影響を及ぼす可能性があります。

コーキングの工事工程
コーキングには「打ち替え」と「増し打ち」の2つの工法が存在します。
打ち替えは既存のコーキング材をすべて取り除くのに対し、増し打ちは既存のコーキング材を残したまま新しいコーキング材を充填していくという違いがあります。
劣化が進んだコーキングに増し打ちを行っても、コーキング材同士が馴染まずにすぐに剥がれてしまう可能性があるため、基本的には打ち替えが行われます。
また、コーキングと外壁の塗装工事を行う順番によって、「先打ち」と「後打ち」に分けられます。
コーキングを行った後に外壁を塗装する場合は先打ちとなり、コーキング材の上に塗膜が形成されることになります。反対に外壁の塗装工事の後にコーキングを行うと後打ちになり、塗膜の上にコーキング材が充填される形になります。
先打ちはコーキング材が塗膜に保護されるため、紫外線による劣化が起こりにくいというメリットがあります。しかし、外壁塗料の柔軟性がコーキング材より低い場合、外壁材の振動・収縮に塗膜が追随できず、コーキング材は無傷であっても塗膜の表面にひび割れが発生してしまう可能性があるのがデメリットです。
後打ちであれば、建物の動きによって塗膜がひび割れてしまう心配はありませんが、塗膜の保護がないのでコーキング材が劣化しやすいという問題があります。
どちらも一長一短ではありますが、基本的には紫外線による劣化を抑制できる先打ちが行われることが多いです。
コーキングの工法について解説したところで、今度はコーキングの具体的な工事工程(今回は打ち替え・先打ち)をご紹介したいと思います!
①既存のコーキング材を取り除く
既存のコーキング材にカッターで切れ目を入れたら、手や工具を使って剥がしていきます。

②養生
コーキング材が外壁に付着しないよう、施工箇所のまわりに養生テープやマスキングテープを貼って保護します。
このとき、テープを適当に貼ってしまうと、コーキング材をまっすぐに充填できずに汚い仕上がりとなってしまうので、該当箇所に丁寧に貼り付けていきます。
③プライマーの塗布
施工箇所にプライマー(下塗り材)を塗布することで、下地とコーキング材の密着性を高めることができます。
しっかりと密着させられればコーキング材の耐久性が向上し、剥がれなどの症状を未然に防げるため、コーキングの耐用年数を左右する非常に重要な工程となっています。

④コーキング材の充填
コーキングガンと呼ばれる専用工具を用いて、施工箇所に新しいコーキング材を打ち込んでいきます。
空洞ができてしまわないように、少し多めの量が充填されます。

⑤ヘラでならす
ヘラを使用して、余分なコーキング材を取り除いて均等にならします。
コーキングの仕上がりに直結する工程でありながら、コーキング材が乾き切る前に完了させる必要があるので、丁寧かつスピーディーに行わなければなりません。
⑥養生の撤去、乾燥
養生テープやマスキングテープをすべて剥がし、乾燥させます。
外壁の塗装工事に備えてコーキング材をしっかりと硬化させなければならないので、約1日程度の乾燥時間が必要となります。
コーキング材が完全に乾燥したら、外壁の塗装工事が始められます。外壁塗装の工事工程については過去のコラムで解説させていただいておりますので、よろしければそちらもご参照ください。
「外壁塗装の工事工程について解説!」(https://kensho-yokohama-tosou.com/success/1745/)
まとめ
以上、コーキングの役割とコーキング・シーリングの違い、具体的な工事工程について解説させていただきました。
コーキングは「目地や隙間部分からの雨漏りの発生を防ぐ」「外壁材同士の衝突・破損を未然に防ぐ」という役割を持っており、建物全体の耐久性に大きく関わる部分となります。
普段あまり目を向けられることの少ない箇所かもしれませんが、外壁の目視でのチェックに合わせてコーキングにも注目されてみることをおすすめいたします。そのときにコーキングの肉やせやひび割れなどの症状が見られたら、早めのメンテナンスをご検討ください。
弊社はご自宅の現地調査と見積もり作成を無料で承っておりますので、コーキングのことで気になる点がありましたら、ぜひお気軽にご相談ください!